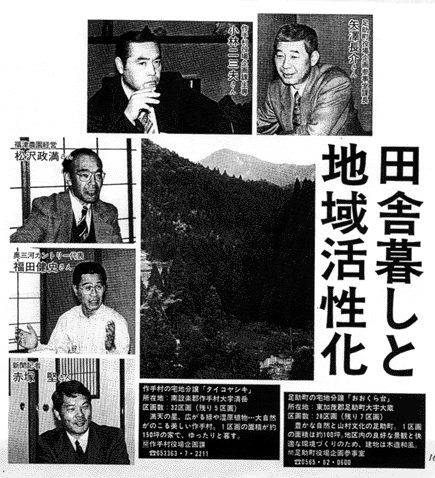
| 物理的な利便さを求めて、人が都会へと集まる流れのなか、広い住空間や自然に囲まれた生活が得られると人気の田舎暮し。一方、過疎化対策のひとつとして、豊かな自然をもった自治体が宅地分譲を実施し、注目を集めています。今号は、田舎暮しと地域活性化について語っていただきました。 田舎暮らしに求めるもの、田舎暮らしが求めるものは…。 | |
| まちづくりにつながる宅地分譲 | |
| 赤塚 | 福田さんは鳳来町へIターン。松沢さんは、新城に、37歳で横浜からUターン。田舎に移り住むには仕事や病院などの問題もあるでしょうね。 |
| 小林 | タイコヤシキの宅地分譲の時も官公庁からの距離など地理的条件をきちんとしないと難しいと感じました。実際に売り出すと、学校やマーケットは必須条件として質問されますね。 |
| 福田 | それほど問題じゃないんだけど、引っ越す前は、病院・学校・買物を非常に気にしますね。 |
| 矢澤 | 一方、山菜を根こそぎ採っていったり、ゴミを捨てていくとか、山に住まう礼儀を知らない人も多い。 |
| 福田 | 会員制で田舎不動産を扱っていますが、会員さんが住宅を求める場合でも、8割ぐらいは田舎暮し不適格者という感じ(笑)。安くて広い土地という部分が強く、どんな暮し方をしたいのかを全く持っていない人も。 たくさんの物件を見ていけば方向性が決まってくると思いますが。 |
| 赤塚 | その中で、田舎暮しのアピールはどうされていますか。 |
| 福田 | 例えば、仕事は一つの生活の糧を得るものなど、価値観が変えられると意外と楽にいい暮しができますよ。 |
| 松沢 | お金を最優先にしたら、かなり厳しいですが、いかに豊かな生活をするかという視点にたてば、中山間地域の農的な暮しほど、豊かで楽しい暮しはないでしょう。 |
| 赤塚 | 足助町も作手村も宅地分譲をしていますが、目的は何ですか。 |
| 矢澤 | 1つは人口対策。外から招くのと、次男、三男など足助で生まれた人たちの住宅という二面性があります。 街から山へ住まう中での、生きざまや、農林業や土に触れるだけではない、山に住まう豊かさ、文化を逆に与えてほしいのが2つ。 3つめが、民間開発の悪い奴がたいへん入ってくるので、きちんとした宅地を買っておかないと損だぞ!というモデルをやりたい。 |
| 松沢 | 10年もすれば、家が傾いてしまいそうな不十分な造成もあるとか。 |
| 矢澤 | そう。山に住まうという視点もなく、ただ安いという魅力だけ。誇りを持って住んでもらうには、きちんとした宅地造成をすべきだと思う。 |
| 赤塚 | 足助は一区画が100坪以上、作手は150坪以上と広い。 |
| 矢澤 | 広さが何を生み出すかといえば、2世代、3世代と暮らすことも可能だし、もっと大事なのが、土・日曜に家でやる仕事があること。街の中に40坪ぐらいの土地いっぱいに家を建てれば出かけるしかない(笑)。でも、100坪あればいろいろできる。この豊かさによって、地域の人々と結びつく。 |
| 小林 | 初めは新しい行政区を作る話もあったが、それでは子供たちのお祭りだとか地域の行事に携われないから、一つの行政区で、作手の悪さもあるだろうが、良さも知ってもらおうと。 |
| 福田 | 足助町は木造で白壁造り、しかも石積み(間知石)という条件付き。ネックになりませんでしたか? |
| 矢澤 | 10、20年…と住むうちに俺の家だと誇れるんじゃないかな。問い合わせも300件ぐらいありましたよ。 ネックと言えば、3年以内に建てるという条件が厳しいわな。 |
| 福田 | 投機目的では困るし、仕方ない。 |
| 矢澤 | 家作りを知らない若い世代が、土地を所有してから勉強に取り掛かってもいいように、今後は期限をあと2年ぐらい延ばすとか緩やかに。でも、木造など個性的な条件は、将来誇れる家造りの点で重要だから緩めない。 |
| 福田 | 民間なら早く完売して資金回収する必要があるけど、せっかく町がやるんだから、売れ残っても、住宅がないから街へ出ていく村の若い人達のために長期間残しておくのもいい。 |
| 矢澤 | たかが30戸じゃない、早く売って、次の手を打ちたい(笑)。ただ、行政が宅地造成をやる意味はそういうことに視点を置くことだよ。 |
| 赤塚 | まちづくりですね。まちづくりに、人口増などいろいろなメリット、一石何鳥を考えての宅地造成。 |
| 矢澤 | 街の土地が騰り、家が小さくなる…人口は増えたが、日本人として誇れる人がどれだけいるか。せめて80坪ぐらいの宅地分譲をしていれば、住み方や物のとらえ方に潤いがでたろうに。「きちんとできるのは山だ!」というぐらいの自惚れを持たないと(笑)。 |
| 真の豊かさとは何か | |
| 小林 | 商業ゾーンや、遊ぶ場所を整備しないと若者はついてこないでしょう。もちろん、伝統は大切ですが、若者の気持ちを吸収しすることも必要。 |
| 松沢 | 一方、街の人を呼ぶとか、村の中の若い人の活性をあげたい時に大切なのは、若い人達がどういうよさを感じ、住みたいのかをとらえて、最大限にいかす形にすること。何を若者にPRすべきかを根本的に考え、拙速に結論を急がなくてもいいと思います。 |
| 矢澤 | すべて足助町の中でカバーする必要はない。どうやっても若者が望むだけのネオンをつけた店なんかできないんだから(笑)。仕事なら豊田や名古屋に通えばいい。文化施設、買物、病院でも一緒。もう少し住まう見方をわきまえてくれないと、利便性がない=住まう豊かさがないになってしまう。 これを理解してもらうのがお役所のソフト的な仕事。足助の総合計画は“山里に暮らす豊かさを求めて”。与えられるものではなく、住む人が探して創っていくものだから。 |
| 赤塚 | これまで都会暮しでも、田舎暮しでも、日本人は豊かさを求めて動いてきたような気がするんです。 老後に田舎暮しを求める人がいますが、求める豊かさはありますか。 |
| 福田 | 村ではお年寄りの知恵や経験が十分発揮でき、役割もあり、大切にされているからいきいきしている。 |
| 矢澤 | これまでの高齢化社会の福祉は、ご苦労さんだったから遊んでおいでって感じだった。足助では、『ZiZi工房』『バーバラはうす』で、お年寄りにソーセージやパンを作ってもらっている。その人達に、僕は「もうひと働きして、足助に住まう豊かさを実践してほしい」と、言うんだ。 |
| 松沢 | 農業でも地域のよさを最大限にいかし、誇りを持って消費者に提供できるものを作れば理解されます。ソーセージやパンもこだわりを持って作っているから人気があるんでしょう。 |
| 矢澤 | 山に来てどんな生き方をするか。創造性のない人は来てもあかん(笑)。 |
| 松沢 | 田舎暮しのよさを最大限にいかす意志のある人は可能性が大きい。そうじゃない若い人、小さい人に命の大切さや自然の循環に配慮した生活を見て、育つことも期待したいです。 |
| 福田 | 田舎暮し=農業という人が多いけど、職業として成り立ち難い。 家庭菜園なら、趣味でやると楽しいし、矢澤さんがいうところの、土・日曜日の農業です(笑)。 |
| 松沢 | 趣味的な農業、生きがいとしての農業、高齢者対策としてもメリットがあるし、地域自給を高めることにもなり、自然環境もよくなる(笑)。 |
| 矢澤 | 新しく来た人は、100坪あれば半分農地にできるけど、従来からいる人は、先祖から受け継いだ畑を「耕す」使命感がある。この義務感・使命感を、どうやって面白く、豊かな農業に切り替えるかが大切。 |
| 松沢 | 以前は高いお金を払ってアスレチックジムに通っていたんだけど、今は堆肥運びなど、空気のよい所で、ただで清々しい汗がかける。でも、臭い堆肥を汚い格好をして…と考えると最悪(笑)。ちょっと視点が変えるだけで、ずいぶん違いますよ。 |
| 矢澤 | ずっといるとその発想はムリ。そういう楽しさ、豊かさ、面白さを、都会から来た人に提案してほしい。 |
| 田舎暮しを発信 | |
| 赤塚 | 都会では非常に機械的な文明があって、会社員でも自営業者であれ、それぞれの部品を生産しているに過ぎない。だが、田舎では各人が役割を果たさないと、全体的にうまく稼働しない。それによりコミュニケーション、人とのつながりができる。 |
| 矢澤 | 一方、時代にあったコミュニティーを作り上げていく力も必要。これからもいろいろな集落に宅地分譲して、新しい血を入れることで、新しいルールを構築したい。 田舎だからすべていい、オールマイティーではないと思う。 |
| 福田 | でも、地価が安い、安価な建売が出ているという理由で、田舎暮しを志向しない人で人口が増えても、ガタガタになるだけ。 |
| 矢澤 | 足助や作手は、都市に近いから人が住む点では武器でもあるが、開発という名に隠れて、本来失ってはいけないものを失う面も抱合せて持っているのは恐ろしいことでもある。 |
| 福田 | 本当に田舎暮しを志向する人なら60歳過ぎても、街でのノウハウを持ち込んでくれば、刺激になる。 |
| 小林 | 行政からすると高齢化率が25、26%では、これまたまずい(笑)。 一方、宅地を買う資金がない若い子のために、集合住宅を去年1棟、来年も1棟整備していく計画です。 |
| 松沢 | 農地法など難しいですが、農業をめざす若い人のために、借地借家など、柔軟な対応ができると、村の活性化の点でもいいと思います。 |
| 福田 | 真剣にやるなら農地を貸す人はいるけど、トラブルが起こると「何であんな奴に貸したんだ」という話になるから借家は難しいでしょうね。 |
| 矢澤 | せっかくの家が朽ちていくだけだから、法律的には難しいけど、田舎の定期借地権のような新しいルールを作るのもいい。また、地山を残した森林付分譲、建売分譲をできないかな。 |
| 小林 | 若い世代はアパートに住んでいて、建て始めるとローンとアパート代が二重の負担になるから建売を考えたけど、建物は償却物だから難しい。 |
| 赤塚 | 田舎暮しと地域活性へのそれぞれの意見をお願いします。 |
| 福田 | 不景気になって田舎志向が増えています。みんなに呼び掛けるけど、みんなに来てほしいのではなく、創造力のある人、自分から楽しみを見つけられる人なら田舎は楽しいですよ。 |
| 松沢 | 田舎も今までと同じ考え方でいたら、子供もよそへ出てしまい、ますます過疎化になる。生活している人が地域のよさをいかして生きること、誇りを持てるような方向性を出すことが重要。それが人口増なり、魅力ある人が集まる結果になると思います。 一方、やってくる若い人の持つ、価値観や個性の多様性を大事にする土壌を育んでほしいですね。 |
| 矢澤 | 山に住まうことの豊かさを、山の人も都会の人も、お互いに勉強する場が必要。住宅開発では、人がくればいいのではなく、きちんと住んでいく張り合いがある住宅地を作ること。 もう1つが、山に住む人はカッコイイ、ハイクラスだと思われる、自然と調和させて生きているんだという部分も必要だと思うな。 |
| 小林 | いまの人口を維持しようと、定住政策をやっているわけですが、今後は村に刺激を与えてくれる人材誘致をして、活性化したいと思っています。 若い人もみんな「超一流に暮してやろう」という気概でやっていますよ。 |
| 赤塚 | 今までは、他の人に田舎暮しを説明・発信できなかったけど、いろんなノウハウを持っているんですから、積極的に出していけばいいと思います。今日はありがとうございました。 (額田郡額田町『大松滝山荘』にて) |
